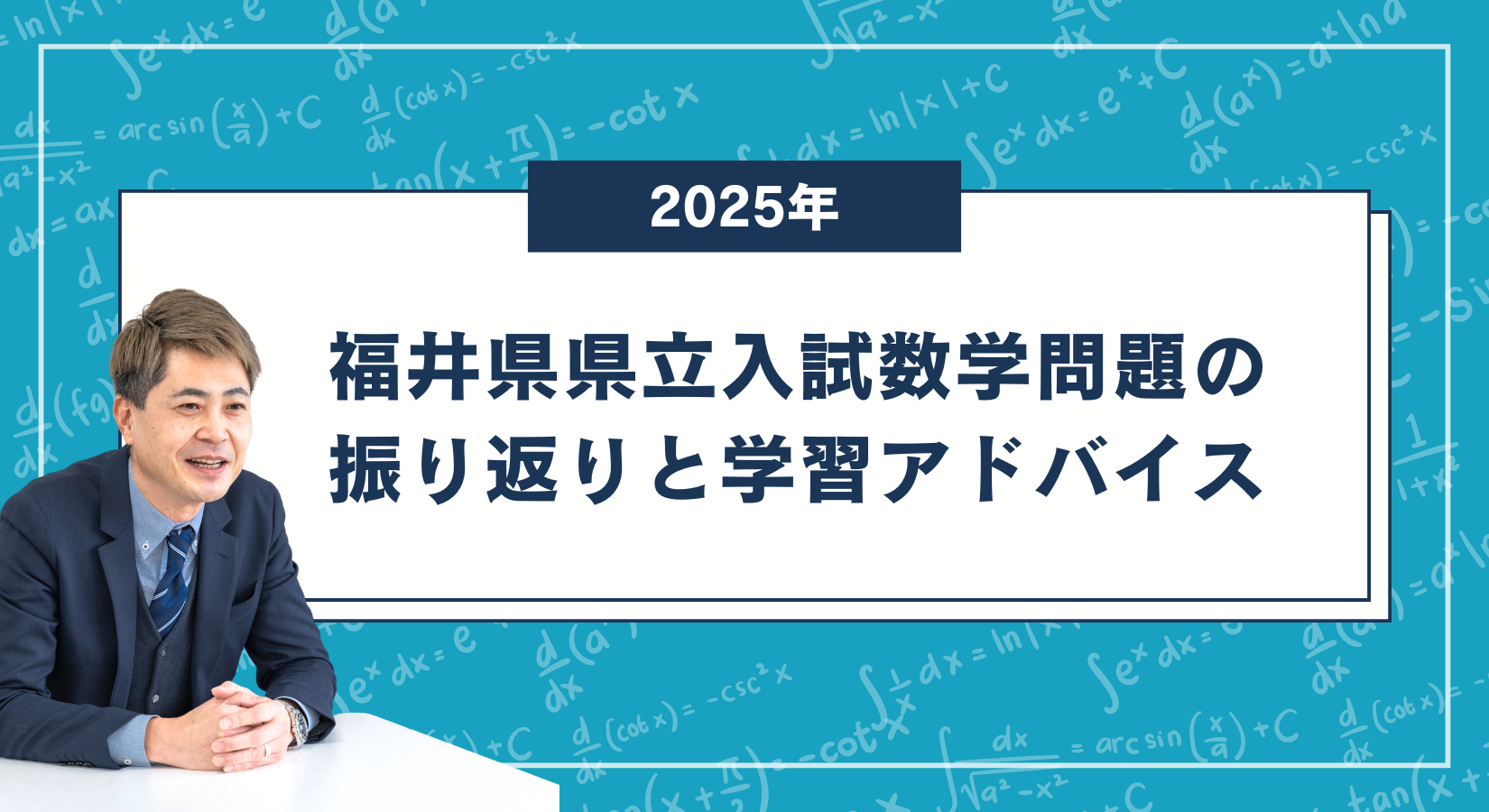令和7年度(2025年)福井県県立入試数学問題の振り返りと学習アドバイス
こんにちは、英心うえの塾の河合です。▲▲画像をクリックすれば動画も見られます▲▲
今回は2025年度の福井県県立入試数学問題について振り返り、試験の内容を詳しく解説していきたいと思います。
総評
まず初めに、今年の福井県の数学問題の難易度についてですが、全体的には「例年並み」または「やや優しい」と感じられました。この評価は私の主観だけでなく、生徒からのフィードバックを元にしたものです。問題量や問題の質に関しては、例年と大きな違いはなく、特に難易度が高かったという印象はありませんでした。
近年恒例の「説明せよ」という問題が出題され、今年もその形式がしっかりと続いています。この問題は、計算だけでなく、しっかりとした論理的な説明力が求められます。計算問題にばかり注力するのではなく、数学的な理解を深め、人に説明できるような知識を身につけることが大切です。
大問1
大問1は、例年通り小問集合に関する問題が出題されました。問題数は約7問から8問で、大問1の配点は40点と大きいです。特に、連立方程式や因数分解、データの分析といった基礎的な内容が出題され、普段の勉強をしっかりと反映できる問題でした。説明せよという問題は、連続する偶数の2乗の和に関するもので、答えが一通りではなく、複数の解が考えられる問題でした。このように、解法を導く過程を重視した問題もありました。
大問2・大問3
大問2では確率の問題が、大問3では規則性に関する問題が出題されました。確率の問題では、6枚のカードから1枚ずつ取り出すという問題で、樹形図や表を使った解法が求められました。規則性の問題は、紙を並べていくという典型的なタイプの問題で、順番や枚数に関する規則を見つける力が問われました。
大問4
大問4では、関数とその応用に関する問題が出題されました。特に、点の移動に関する問題では、面積や体積が1次式や2次式で表されることを理解し、グラフの形状を予測する力が試されました。後半のXの範囲問題は少し難易度が高く、特に分数を伴う複雑な数値が絡んだため、難しく感じた生徒も多かったと思います。
大問5
大問5では相似と円の性質に関する問題が出題されました。特に、相似の証明問題は、円周角の定理や錯角を使う問題で、基本的な知識をしっかりと活用する力が問われました。後半の辺の比に関する問題は、難易度が高く、時間がかかることが予想される問題でした。このような難易度の高い問題があることを前提に、時間配分を意識しながら解くことが重要です。
今後の数学の勉強法
これから入試に向けて勉強を進める皆さんには、以下の点を意識して学習してほしいと思います。
1.理解の深化
数学の授業を聞いて「へー、そうなんだ」という感想を持つことは危険です。この「へー」という感想は、理解が不十分な証拠です。しっかりと自分の中で納得できるまで学び、知識を定着させましょう。例えば、「三角形の面積は底辺×高さ×1/2」といった基本的な公式に対しても、「なぜそうなるのか」を自分の言葉で説明できるレベルを目指しましょう。
もし授業でわからないことがあった場合は、そのままにせず、必ず教師に質問したり、参考書で調べたりして解決しましょう。「なんとなく覚えておこう」ではなく、すべての疑問を解決していくことが大切です。
3.しっかり過去問演習
過去問をしっかりと演習することで、出題傾向を把握し、試験本番に向けての実力を高めることができます。特に、難易度が高い問題があることを意識して、時間配分や解き方を工夫していきましょう。
まとめ
今年の福井県県立入試数学の問題は、全体的に見て例年並みかやや優しい印象でしたが、確実に理解し、論理的に説明できる力が求められる問題が多くありました。今後、受験を控える中学生のみなさんには、基礎力を固め、問題を解く過程でしっかりと納得しながら学習を進めることをお勧めします。
皆さんが数学を楽しんで、そして自信を持って入試に挑めるよう応援しています!
体験授業&個別相談 受付中!
「勉強方法に不安がある」「効率よく成績を上げたい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください!