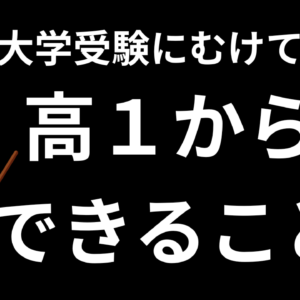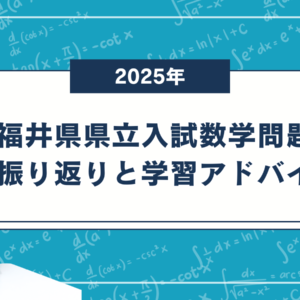【高校1・2年生向け】数学が苦手な人へ ― サクシードを使いこなす勉強法とは?

こんにちは。英心うえの塾の河合です。
今日は高校1年生・2年生の皆さんに向けて、「数学の効果的な勉強の仕方」についてお話ししたいと思います。
先日、藤島高校に通う2年生の生徒たちと面談をしました。
みんな真面目に勉強しているのに、数学のテストで思ったような点が取れない。
なぜなのか?話を聞いてみると、ある共通点が見えてきました。
サクシードは「やった」だけでは足りない
みなさんご存知の「サクシード」。学校で配られている問題集ですよね。
多くの生徒が「一通りやった」と言います。ところが、結果が出ていない。
それはなぜか? 実は、「やった」ことと「できる」ことの間には大きな差があります。
数学は、理解しただけでは定着しない科目です。感動的に「なるほど!」と思ったとしても、それを思い出して再現できる状態にしておかないと、テストでは使えません。
数学は「覚える」フェーズが必要!
数学は、「理解 → 覚える → 定着 → 応用」という流れで学びます。
たとえば漢字の勉強は最初から覚えることが目的ですが、数学はまず理解から始まるんですね。でもそのあと、「覚える」段階を飛ばすと力がつきません。
つまり、解法を「知っている」だけでは不十分。
「こういう問題のときは、この解法を使う」と、セットで記憶しておく必要があるんです。
サクシードを分別しながら進める
じゃあ、どうやって勉強すればいいのか?
まず、1回目のサクシードは“分別”と割り切ることです。
☺️スラスラ解ける → 解けたと判断してOK!
😨3分考えても無理そう→即、解説を読みましょう!
ここで「自力で解きたい」と思って、10分15分粘ってしまう人が多いんですが、それは非効率。 “知らない解法”をいくら考えても出てこないんです。最初は「分別」に徹し、解けないものは理解して覚える、というフェーズに移行してください。
付箋で“わからなかった問題”を管理しよう
サクシードで解けなかった問題には、付箋紙を貼っておきましょう。
⭐️月〜金:授業に合わせてサクシードを進める
解けなかった問題 → 解説を見る → 付箋を貼る
⭐️土日:貼った付箋の問題をもう一度解き直す
こうすることで、「どの問題が自分にとって難しかったか」が見える化されます。
そして、週末にしっかり復習して付箋を剥がしていく。それが積み重なって、本当の意味での「定着」になります。
授業中の姿勢も大事!
授業の受け方にもコツがあります。
✏️ 授業中、解けなかったら勇気を持って鉛筆を置こう!
授業中に「この問題を解いてみて」と言われること、ありますよね。 時間内に解けないときは、解説が始まったら潔く切り替えて聞くことに集中してください。
よくあるのが、「あと1分で解けそう」と思って解説を聞かず、その結果どちらも中途半端になるパターン。これは絶対に避けたいです。
わからなかったら聞く・覚える。これが数学では最も大切なスタンスです。
解法の「着想点」を意識しよう
数学の問題は、「どうやって解き始めるか(着想)」が最重要ポイントです。
答えまでの計算は、実は中学レベルのことが多い。でも最初に「どう解くか」のアイディアが出ないと、計算までたどり着きません。
だからこそ、問題が解けたあとも、「この問題のポイントはどこだったか?」と振り返る習慣をつけましょう。
高1・高2は「色鉛筆を揃える」時期
最後に、こんなたとえ話を。
数学の問題集(サクシード)は「色鉛筆」のようなものです。
1問1問が違う色で、それを丁寧にそろえていくのが1年生・2年生の勉強。
そして入試問題というのは、「海の絵を描きましょう」「森の絵を描きましょう」と言われるようなものです。
色鉛筆(=知識や解法)が揃っていなければ、描くことすらできません。
📝まとめ
- サクシードは「理解→記憶→再現」の流れを意識
- 1回目は分別、解けないものは早めに解説を見る
- 授業は「聞く切り替え」が肝心 • 着想点を大切に、復習で記憶に定着させる
- 色鉛筆(知識)をしっかり揃えておくと、入試の絵が描ける!
高1・高2のうちに、サクシードをしっかり活用し、知識を「使える力」に変えていきましょう。応援しています!
無料体験授業&無料受験相談 受付中!
「受験勉強の方法に不安がある」「効率よく成績を上げたい」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください!