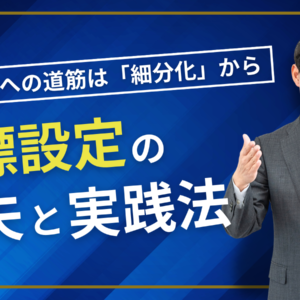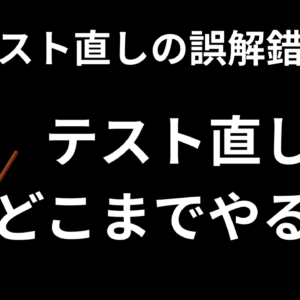【福井県高校入試・英語 徹底分析ブログ 】〜“受かる力”だけでなく、“本物の英語力”を育てるために〜
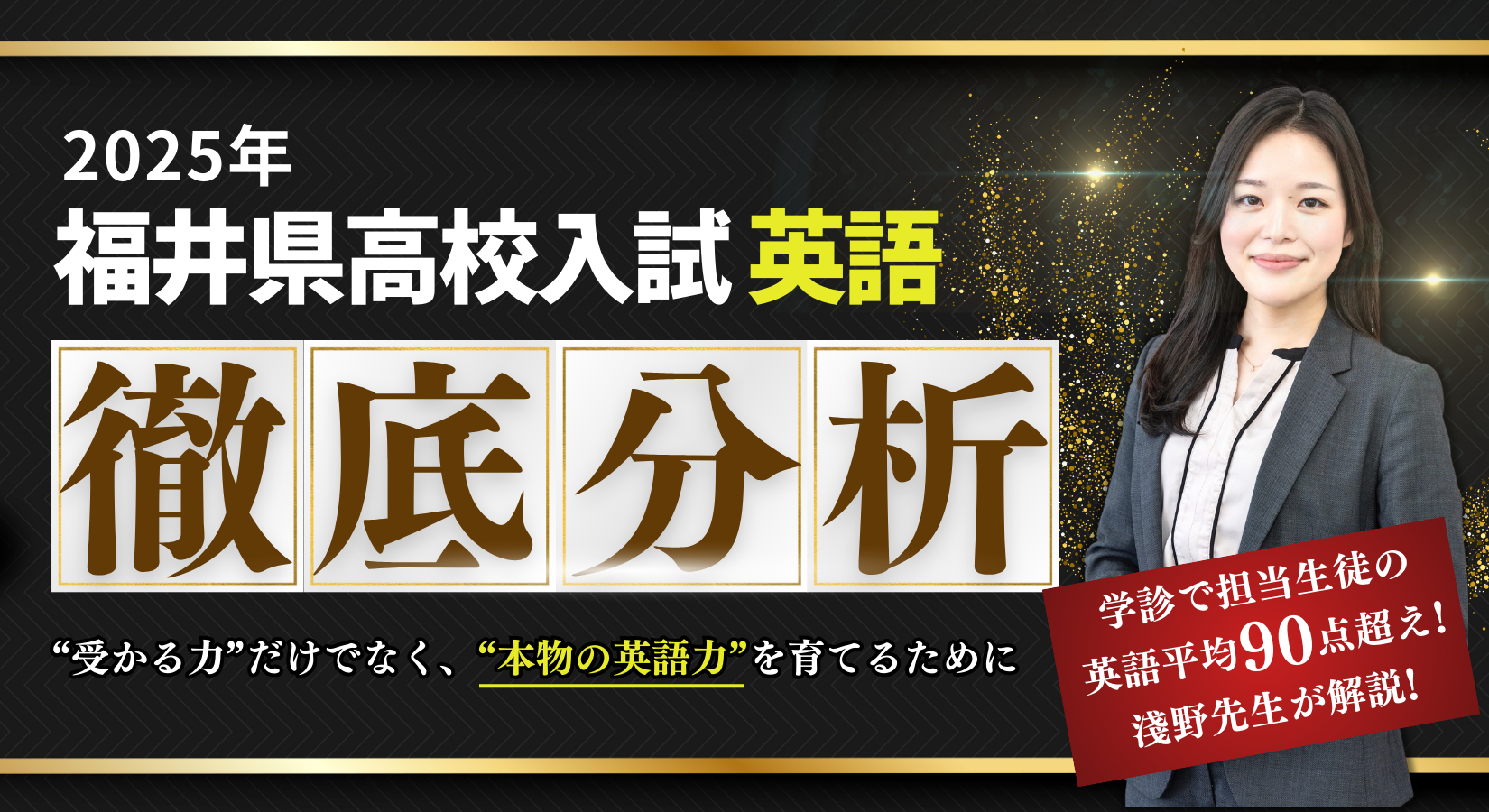 こんにちは。英心うえの塾 二の宮本校の淺野です。▲▲画像をクリックすれば動画も見られます▲▲
こんにちは。英心うえの塾 二の宮本校の淺野です。▲▲画像をクリックすれば動画も見られます▲▲
まず最初に少しだけ自己紹介をさせてください。
私はこれまで、英語という教科を通して、ただ“覚える”だけではなく、“考えて伝える”ことができる力を育てる指導を大切にしてきました。
昨年度、私が担当していた中学3年生の生徒たちは、県内全域で11月に実施される『学力診断テスト』で、英語の平均点が90点を超えるという結果を残してくれました。
これは決して簡単なことではありませんでした。日々の学習の中で「思考する力」「表現する力」「英語を使う力」を生徒一人一人が鍛え続けてきたからこそ出せた結果です。そして私は、福井県の入試英語においても、この3つの力こそが真に求められていると確信しています。
このブログでは、福井県の2025年度高校入試をもとに、入試がどんな力を求めているのか、その中で子どもたちがどこでつまずきやすいのか、そして私たち英心うえの塾がどう向き合っているのかを、本気でお伝えしていきます。
【1】英語は、もはや“暗記科目”ではありません
一昔前の『高校入試』を経験した私たち世代にとって、英語といえば“文法を覚える”“単語の意味を覚える”といった暗記中心の科目だった方も多いのではないでしょうか。
しかし、今の高校入試英語は、まるで別物です。
求められるのは、英語を「知っているか」ではなく、「使って伝えられるか」。
例えば、英語の文法や単語を覚えても、それを実際に使って自分の考えを表現したり、他人とコミュニケーションを取る場面では、その力が試されるのです。英語を「知っている」だけではなく、しっかり「使える」力が必要だということです。
-
自分の考えを英語で書く力(表現力)
-
論理的に英文を読み取り、要点を理解する力(読解力)
-
会話や説明を聞いて判断する力(聞き取り+推論力)
まさに、“思考力・判断力・表現力”の複合科目です。
もはや英語は、受け身でなんとなく取り組んで身につく教科ではありません。
【2】入試の全体像と配点構成
2025年度(R7年度)の福井県高校入試の英語科目は、以下のように構成されていました。
【試験時間】60分(うちリスニング 約14分)
【大問構成と配点(推定)】
-
大問1:対話文読解(会話+グラフ)……25点
-
大問2:自由英作文(30語×2文構成)……20点
-
大問3:長文読解(ストーリー)……25点
-
大問4:リスニング(選択+記述)……30点
▶︎ 読む力:約50点(大問1・3)
▶︎ 書く力:約25点(大問2・4の記述)
▶︎ 聞く力:約25点(大問4)
合計:100点満点
単なる読解や単語力ではカバーできない、複合的な力が満遍なく配点されているのが特徴です。
また、とにかく“読む量が多い”というのも福井県入試英語の大きな特徴です。
R7年度では、問題文・設問・選択肢などすべて含めると、テスト中に生徒が目にする英語は約1800語。
リスニングの14分を除いた残りの約46分で、それらを読み、解釈し、書きながら処理しなければなりません。
これはつまり、1分間に約39語を処理することが求められているということです。
読むだけでなく、選び・書き・判断する——そんな“高い情報処理能力”が試されているのです。
この負荷感は、英検準2級〜2級レベルに匹敵します。
想像以上に、「英語力」だけでなく「思考力・読解戦略力」まで問われるのが、今の福井県入試英語なのです。
【3】読む力は「文の表面」ではなく「心の裏側」まで
高校入試英語の長文読解においては、単に文の内容を理解するだけでは不十分です。特に入試では、登場人物の感情や背景を読み取り、物語の中での心情の変化を把握する力が求められます。この力が必要な理由は、受験生が単に情報を読むのではなく、内容を深く理解し、細かなニュアンスまで読み取る能力が求められているからです。
例えば、心情の変化を読み取る問題は、入試で求められるのはただの『情報』を得ることだけではなく、物語の中の登場人物の気持ちや背景を理解する力が必要だからです。これにより、実際の英語を使ったコミュニケーションでも、相手の感情や意図を理解できる力が養われるのです。
では、具体的にどういった問題が出題されるのでしょうか?
▶︎ 令和7年度 大問3 より
ミホの心情変化を表す文を、本文の流れに合わせて並び替える問題。
【選択肢】
ア:I am not satisfied with my role and want to leave the dance group.
イ:I am sure that I can do something for the dance group.
ウ:I am very happy to hear nice things from the dance group members.
エ:I want to enjoy dancing on the stage.
これは、ただの“順番問題”ではありません。
本文のどの場面で、彼女が「迷い」「希望を持ち」「仲間の言葉に動かされたのか」、その“感情の流れ”を細かく追う必要がありました。
つまり、「誰が・いつ・どんな気持ちだったのか」を読み取る、“深い読解力”が問われていたのです。
【4】書く力は「型」+「自分の考え」
入試の英作文問題では、単に「英語で書けるかどうか」だけでなく、自分の意見を整理して、明確に表現できる力が求められます。これは、単に英語を知っているだけではなく、英語を使って思考し、伝える能力を測る問題だからです。
今年度は、ボランティア活動に関する意見を、60語程度(30語程度×2)で表現する問題が出題されました。
例えば、ボランティア活動で『環境保護』について意見を述べる場合、単に『環境を守りたい』と述べるのではなく、その理由や具体的な行動(ゴミ拾いをするなど)を説明できることが大切です。
▶︎ 出題:あなたがボランティア活動をするなら、どんな活動をしたいか。それはなぜか。
【出題形式】
-
30語程度の英作文を二つ
-
登場人物になりきり、対話に合わせて空欄部に考えを書く(1文目:主張/2文目:理由/ 3文目:具体例や経験)
【採点のポイント】
-
主張にしっかり答えているか(What do you want to do?)
-
理由が書かれているか(Why?)
-
主張をサポートできるような、具体例や経験を述べることができているか
-
英文として成立しているか(文法・語数)
-
オリジナリティがあるか
このような問題では、単なる知識ではなく、自分の意見を明確に英語で表現する力が試されます。また、ボランティアに参加した経験のない生徒も多いなかで、未経験の事柄についても、想像し自分の言葉で具体的に表現する力が求められています。
【5】聞く力は「瞬発力」と「表現力」両方が必要
リスニングの問題では、単に聞き取る力だけではなく、聞いた情報を瞬時に理解し、それに基づいて答える力が求められます。特に、複数人による対話の音声を聞いて内容を整理し、その上で正確に答える能力が重要です。これが必要な理由は、英語を使った会話の中で情報を効率的に処理する力が問われるからです。
では、どんな問題が出題されるのでしょうか?
▶︎ リスニング全体の特徴
-
大問1の一部問題のみ【1回読み】→即時判断力が問われる
-
大問2〜4は【2回読み】あり
-
最終問題は、聞き取った内容に対して「3文以上の英語で自分の意見を伝える」記述式
特に記述問題は、音声をただ理解するだけでなく、
「問いに沿って情報を抜き出し、英語でまとめる」までの全工程が求められます。
選択肢問題でも、似ている選択肢が多く、「誰が・どこで・いつ・何をした」かの細部を聞き逃すと正答が出せません。
このように、リスニングはただの聞き取り訓練ではなく、“情報を聞いて処理し、使えるようにする”訓練なのです。
【6】なぜ英語ができないのか——見えにくい壁
「単語を覚えてるのに点が取れない」
「問題を読めば意味はわかるのに、選べない」
そんな声を、私は何度も聞いてきました。
その背景には、次のような“つまずきの本質”があります。
▶︎ 「読めているようで、読めていない」
一文一文の意味はとれても、文と文の関係(因果・対比・転換)をつかめていない。
▶︎ 「書こうとしても、何を言えばいいのか分からない」
意見を持つ経験が少なく、“自分の言葉”がないまま英作文に挑んでいる。
▶︎ 「リスニングが聞こえたのに、答えが出ない」
情報は取れていても、何を根拠に選べばよいか判断軸が育っていない。
▶︎ 「文法も語彙も学習しているのに、点に結びつかない」
“知識”として学んだことが、“運用”できるレベルに達していない。
【7】だから、英心うえの塾はこう指導しています
私たちは、入試で問われている力を、ただ“模試形式”で演習するのではなく、
その背景にある“思考力” “運用力” “言語感覚”を育てることを大切にしています。
📖読む力:
1〜2年生のうちから教科書の本文を丸ごと覚える暗唱指導。意味を理解し、和訳し、自分の言葉で書き直すトレーニングを通じて、「文のつながり」「構造」「要点」の把握力を養成します。
✏️ 書く力:
1〜2年生のうちから「主張+理由+具体例」の型を身につけ、3年秋以降は50本英作文ノック(英心うえの塾オリジナル教材)で、“誰かの言葉”ではなく“自分の言葉”で書けるように。
👂聞く力:
中1からの音読・発音練習、そして中3の毎週リスニング演習。家でも繰り返し聞ける音声データを配布し、耳を育てます。
📚基礎力:
すべての授業で「同じ文法を6回反復できる」設計。学校・家庭・塾で、重ねて練習する設計だからこそ、知識が定着します。
私たちの指導は、“がむしゃらな努力”ではありません。
入試において“意味のある努力”を重ねられるよう、徹底して設計しています。
【8】最後に——“伝える力”が、未来をひらく
英語ができるようになることは、点数を上げることだけではありません。
自分の考えをもち、それを相手にわかりやすく伝えようとする——
その過程が、これからの子どもたちの人生を豊かにすると、私は信じています。
英語力とは、まさに“自分の人生を伝える力”。
英心うえの塾は、ただ点数をとるための塾ではありません。
その先にある“伝える力”を育てる塾です。
今すぐ、無料体験に参加してみてください!
英心うえの塾 二の宮本校 淺野